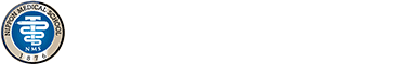我が国における消化器内視鏡診断・治療学の草分けである常岡健二元学長の就任後、68年には世界に先駆けて内視鏡的胃ポリープ切除術を行うなど、消化器病学の進歩に貢献してきた伝統ある消化器内科です。患者の立場に立った心の通った医療を理念とし、食道、胃十二指腸、小腸・大腸、肝臓・胆道・膵臓、内視鏡診断治療、化学療法の6グループが個々に外科、放射線科、病理部との随時連携による集学的診療を目指しています。また、内視鏡センターに常勤医を配置しているため、年間150例を超える重症消化管出血患者に対して常時迅速な対応が可能です。当科では全消化器疾患の診療を担当していますが、その中でも各診療グループの特筆すべき部分をご紹介いたします。
消化管機能グループ
-
診療面では、主に食道疾患を担当しています。多くの紹介をいただくのは、薬物抵抗性の逆流性食道炎、非びらん性逆流症の患者さん、原因不明なつかえ感(食道アカラシアなどの食道運動障害)を有する患者さん、好酸球性食道炎の患者さんなどです。これらの患者さんに対して内視鏡検査、食道内圧検査、食道インピーダンスpH検査、食道造影検査などを行い的確に診断し、病態に基づいた治療を行っています。当科はこれらの疾患に対して、病態に基づく治療を実施できる国内有数の施設の一つです。食道アカラシア患者さんに対しては内視鏡診断治療グループと協力しPOEM (経口内視鏡的筋層切開術) 治療を行っています。研究面では、ガイドラインでの治療が不十分である患者さんの病態、治療に関する多くの研究論文を報告しています。特に近年では、GERD患者において酸曝露を抑制する因子として重要な唾液分泌に関する研究論文を多数報告しています。また現在は食道疾患に加えて、内視鏡下胃機能検査および直腸肛⾨内圧検査も⾏っており、全消化管の機能性疾患に対する診療・研究に取り組んでいます。
胃グループ
-
診療面では、胃・十二指腸の悪性良性疾患を担当し、現在患者数が増加している機能性疾患を多く診療します。研究面では、基礎研究として内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)およびH. pylori陽性胃炎患者におけるCOX-2のSNPに関する研究を行い、機能性疾患である機能性ディスペプシアの臨床研究に関してもこれまで多くの研究論文を報告してきました。最近では難治性の機能性ディスペプシアと早期慢性膵炎がoverlapすることを報告し、超音波内視鏡を用いた早期慢性膵炎の病態研究にも力を入れています。膵酵素を軸とした機能性ディスペプシアと早期慢性膵炎の研究においては多くの症例数を有し、研究報告を行うとともに日々の診療に活かしております。今後も十二指腸の炎症および腸内細菌にも着目し病態解明を目指し、患者様へ還元することを目指していきます。
小腸・大腸グループ
-
診療面では、小腸・大腸の悪良性性疾患を担当します。特に得意とするのは小腸疾患です。小腸は生体内で最も長く面積の広い臓器であり、検査は困難です。しかし、カプセル内視鏡、ダブルバルーン内視鏡の登場により、小腸疾患の診断能が飛躍的に向上しました。当教室ではこれらの機器をいち早く導入し、現在、国内有数の小腸内視鏡検査施設として、1500例を超えるトップクラスの検査実績を誇ります。研究面では、これらの機器による診断、治療に関する論文が報告されています。また、早期大腸がんの粘膜切除術・粘膜下層剥離術など内視鏡的治療、AIによる大腸ポリープ検出率の研究を行っています。炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)、大腸憩室の診療のみならず臨床研究も行っています。
肝臓・胆道・膵臓
グループ-
診療面では肝臓、膵臓、胆道疾患を担当します。得意とする肝疾患はウィルス性肝炎、脂肪性肝疾患、肝硬変、門脈圧亢進症、肝がん治療であり豊富な診療実績があります。研究面では実臨床における諸問題の解決のために、慢性肝炎、肝硬変、門脈圧亢進症の治療成績を様々な角度から解析した多くの研究論文を報告しています。胆膵領域では、内視鏡検査を主体とした多数例の経験があり多くのマンパワーを投入し診断・治療等に力を入れています。
内視鏡診断治療
グループ-
診療面では、効率的かつ高精度な消化管癌に対する内視鏡検査の実施、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)に代表される消化管癌に対する安全で精度の高い内視鏡治療を行っています。また、食道グループの協力のもと食道アカラシアなどの食道運動機能障害に対する内視鏡的筋層切開術(POEM)や、消化器外科とのコラボレーションによる腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS)を積極的に推進しています。研究面では、内視鏡診療支援AIの開発、粘膜下腫瘍に対する高精度な診断法および身体に優しい内視鏡的切除法の開発、バレット食道の病態解明を目指した国内/海外共同研究、安全で確実なESDおよびPOEMの検討など、多岐にわたる研究テーマを手掛けております。
化学療法グループ
-
消化管癌(食道癌、胃癌、小腸癌、大腸癌)と肝胆膵領域の癌(肝癌、胆道癌、膵癌)の化学療法を中心に行っています。切除不能例の緩和的化学療法に加えて、消化器外科や放射線治療科と密に連絡を取りながら術前、術後化学療法や放射線併用化学療法も施行しています。研究面では、治療ガイドラインで推奨された治療法の根拠となった試験の対象から外れるような症例に対する化学療法の安全性や有効性の研究などを行っています。