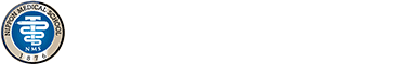肝臓・胆嚢・膵臓グループ
診療の特徴
慢性肝疾患の臨床研究
これまで本邦の慢性肝疾患を占めていたC型慢性肝炎の治療の進歩はめざましく、現在インターフェロンを使用しない内服薬である直接作動型抗ウイルス薬(DAA)が主流であり、非常に高い有効性を認めています。日本医科大学肝臓グループとしては積極的にこの治療を導入しており、また医師会や患者会を通じて啓発活動も行っています。全国でも常にトップクラスの症例数を経験しており、肝臓臨床研究グループでは、実臨床におけるC 型慢性肝炎の治療成績を様々な角度から解析し国内外の学会発表や英文論文の執筆活動をしています。毎年国際学会(米国肝臓病学会、欧州肝臓学会、アジア太平洋肝臓学会など)に肝疾患の研究成果を発表しており、国内でも数多くの研究成果を報告しています。英文論文もC型肝炎、B型肝炎、脂肪性肝炎、肝硬変、門脈圧亢進症関連で当教室よりこれまで60編以上執筆しています。さらに現在、日本医科大学付属病院の肝臓内科グループは国内以外にも、国際的にも著名な米国やフランス、エジプトなどの大学と共同研究も実施中であり日本医科大学の多くの症例のデータは中心的な役割を担っています。また現在日本医科大学として慢性肝疾患における5つの新薬の国内開発試験に参加しております。
胆道鏡(Spy Glassシステム)を用いた胆管疾患の診断、治療
胆道鏡は胆管狭窄や腫瘍性病変を直接観察し、NBIや直視下生検を行うことが可能であるため、胆道疾患の診断に有用です。また、除石困難な総胆管結石症に対しても結石を確認しながら砕石を行うことが可能であるなど、治療⾯でもその有用性が期待されています。当科ではSpy Glassシステムを用いて、さらなる診断能や治療成績の向上、新たな治療法の開発等の検討を行っています。